認知症の母の右足裏の「たこ」が、ここ数年で一番の大きさになった。
わたしが貼るイボコロリで「たこ」を溶かすのが日常なのだが、なぜかうまくいかない。
あまりにひどい時は、近所の外科に母を連れて行き「たこ」をメスで削ったこともあった。
しかしその外科がつぶれたので、今回は盛岡にある「ときいろ・ねいる」さんにフットケア出張を依頼した。
母はなぜ「たこ」が出来やすいかというと、難病であるシャルコー・マリー・トゥース病が原因。
末端が筋萎縮するこの病気の特徴は、土踏まずがあまりないこと。
そのため、足裏と地面の接地面積が小さく、その接地面に集中的に体重がかかって「たこ」ができる。
この病気の人には、「たこ」が出来やすいのだ。
ときいろ・ねいるのメディカルフットケアワーカー中村さんの施術により、このように改善した。(足裏が汚い写真なので、閲覧注意!)


イボコロリは使わないほうがいいらしく、こういう場合はハンドクリームがいいのだそう。
母の足裏はカッサカサすぎるので、かかとも含めてハンドクリームを足裏全体に塗っている。
わたしの足裏もハンドクリームを塗らないと、カッサカサのかかとでパンストが伝線するんじゃないかってレベル。
「たこの痛み」に隠された真実
キレイになった母の足を見て、これはすごい!とまず思った。
それと同時に、ある母の口癖を思い出した。

あれ?ひょっとして「たこ」で足が痛むから、歩きたくなくて買い物に行きたくないと言っているんじゃないか?
本当に強烈な痛みなら母はわたしに訴えるけど、「たこ」程度だと気にならない時間帯も多くある。
「買い物に行きたくない」という言葉の裏に隠されていたのは、「足のたこの痛み」じゃないかとわたしは思った。
認知症の人の「声なき声」ってなに?
医師・介護職、あるいは家族が認知症の人のそばにいたとして、タイミング良く「痛い」「苦しい」と自分の体の異変を教えてくれればいい。
しかし多くの場合、認知症の人は痛み・苦しみを「忘れている」ことがあって、さっきまでは痛みがあったのにそのことを忘れ、介護者に教えてくれないことがある。
病院に連れて行った時とかも、自分の身体の症状を伝えられないことがよくある。
また見栄を張って「大丈夫です」と医師に伝え、それを医師も家族も「そうなんだ」と言って終わることもよくある。
わたしは母と1週間生活するので、その中で「異変」に気づくことができる。でも、通いで介護している方は、週末という短い時間しか一緒にいられないから、「異変」に気づかず、病気やケガを長期に渡って見つけられないことがあるだろう。
こういった認知症の人の「声なき声」は、ときに暴力や暴言という形で現れる。家族もまさか足の裏や体の見えないところで、異変があるなんて気づかないから、暴力や暴言という表面的な部分で反応し、ケンカになってしまう。
家族ではなく医療・介護職といったプロが見つけられるかといえば、在宅なら一緒に居る時間は家族よりはるかに短いので難しい。(勘のいいプロもいる)
それで認知症の人とケンカして、介護者は「もう知らない!」と見放し、認知症の人を放置して病気やケガを悪化させたりする。
最近、白内障の母を眼科に連れて行くことがあるのだが、目もやっかいで介護者が思っている以上に見えていない可能性もある。
その見えないイライラで、暴力的になっているかもしれない。
眼鏡の度数が合ってなくて、暴言を吐いているのかもしれない。
家族はこういった見えない体の異変にも目を配り、さらに抗認知症薬の量の多さも見なくてはいけない。(←薬は見える)
本当に介護する家族は大変だ。
認知症の人の「声なき声」を拾うには?
認知症の人の「声なき声」を拾うには、認知症の人をよく見ておくのと、ちょっとした言動の変化を拾うしかない。
母の入れ歯のカビ、足の裏のたこなど、絶対気づかないところを、たまたま見つけられたのはラッキーだった。
そして、声なき声をキャッチできるだけの「介護者の知識」も必要なのだと思う。
例えば、以前ご紹介した「老人の取扱説明書」という本を読んでみるとか。
アンテナを張って行動していると、勝手に目に耳に飛び込んでくることがある。
あの状態を作るためにも、老いると体はどう変化するのかを知っておく必要が家族にもあるのだ。
しかし家族はそこまで知識がないから、認知症の人の「声なき声」を拾うのは本当に難しい。
でも、言動の変化に気づきやすいのは、長年連れ添った家族の特権ではないか?
おかしいなと思ったら、体の見えない部分「も」チェックしてみると、答えが見つかるかもしれない。
こんな記事を書いておきながら、母がデイで買い物に行きたがらない理由が、「ただ面倒なだけ」という可能性があることを、最後に付け加えておきたい。
今日もしれっと、しれっと。




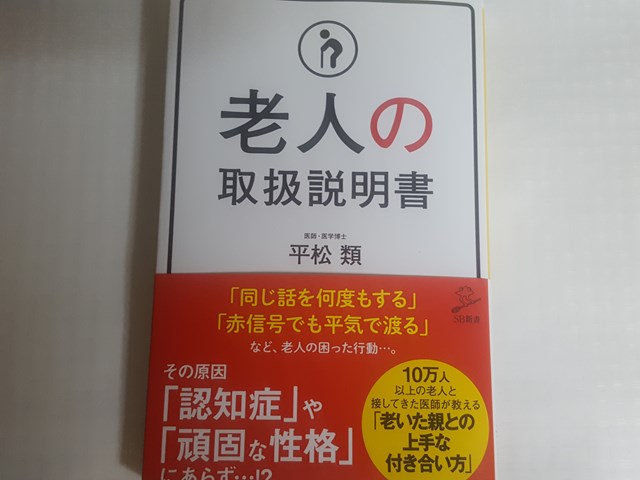


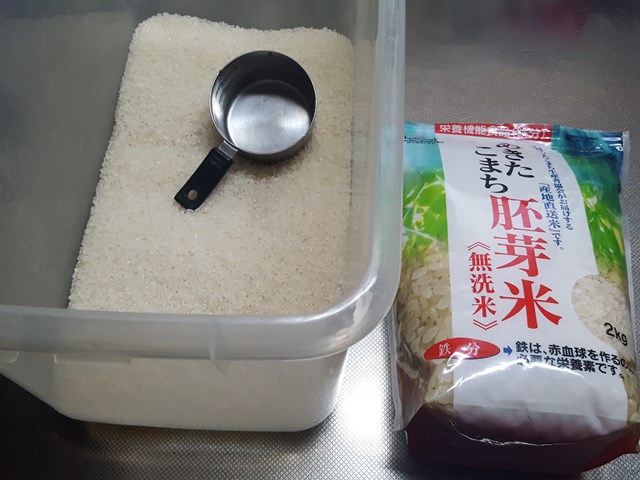






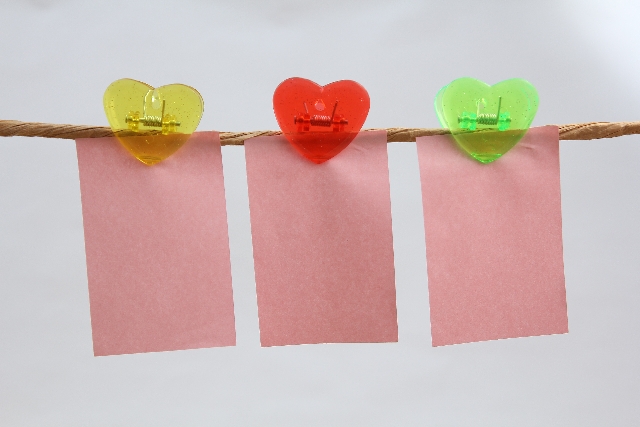




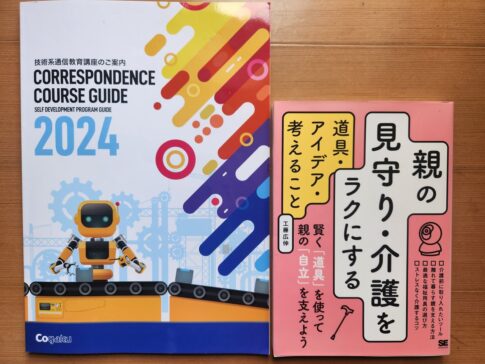


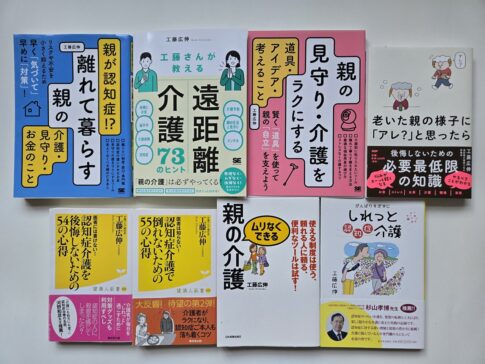










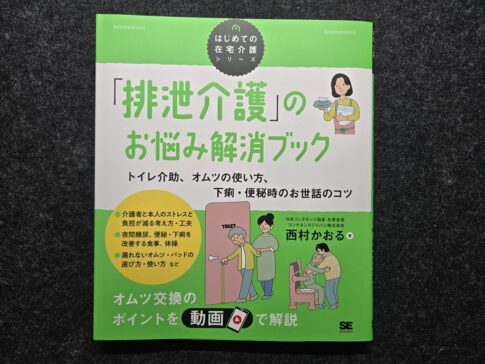
我が意を得たりのお話で、感激です。本当にその通りで、言いたいことと言葉が一致しないみたいで、というか上手く表現出来ない様で…あれ、認知症ってそういう病でしたね❗発言を鵜呑みにせず、しっかり観察した方がいいですよね。ある時、パッと合点がいくのです。うちの場合は、トイレに連れて行ってがなかなか言えずに、ただ呼ぶだけ…なんてこともありました。ただ、家族だからこそ分かるというのは喜びなんじゃないかな❗それに私達が思っている以上に、ちゃんと見て、ちゃんと分かってますよ❗家族だからそう信じられます。知識が足りず、頭が悪くて、にぶい娘なのを詫びながら、今日も励みましょう❗
群青ブルマさま
家族だからこそ分かる喜びという表現 いいですね!
見過ごしてしまいました。声無き声が拾えなくて、
今、病院の堅ーい付き添いベッドでコメントしてます。高齢の糖尿の人は足に傷を作ったらアウトなんですよ!って早く教えてくださいよー‼️
ごめんなさい。お母様 。 血管の不具合絶対治すよ‼️
さゆさま
医療・介護のプロでない場合、どうしても声なき声を拾えないということはあると思います。
一緒に居る時間の中でなんとなく異変を見つけ、プロに聞いたり自分で調べたりして、わたしも自分自身をバージョンアップしている感じですよ。