17日(金)、東京へ帰る東北新幹線のチケットを確保しておりました。しかし、もう少し盛岡に居ることになった経緯を書きます。
かかりつけ医に足の状態を診てもらう
1週間前、実家に帰ってきたとき、母は足が痛いと言っていました。3月末に自宅の居間で転倒して、骨折した影響です。途中再転倒しましたが、レントゲンでは問題ないと言われました。でも6週間経ってもまだ痛いというので、対応することにしました。デイサービスの連絡帳に、足の腫れがあると書いてあったことも影響しています。
まずはものわすれ外来の予約をしていたので、かかりつけ医に相談しました。すると腫れはなく、たぶん大丈夫だけど、気になるなら〇〇病院に行ったほうがいいと言われたのです。
さらに病院の待合室で、いつもお世話になっているフットケアの看護師さんの意見を聞きました。やはり腫れはないとの回答でした。
痛みの理由をはっきりさせたほうがいいと考え、ものわすれ外来から続けて整形外科へ行くことにしました。
整形外科の診断
初診で2時間ほど待ったところで、レントゲン撮影の順番が来ました。車椅子に母を乗せて院内を移動し、撮影。その後診察の順番が来たので、わたしは若い男性医師にこう質問しました。

他の場所は大丈夫ですね。若い人だったら、痛みはなくなっているぐらいの骨折ですけど、80歳だと治りも早くないですから。自重による痛みはまだ続くと思いますが、時間が解決します。転倒から、3か月くらいは見たほうがいいと思います。
翌日は訪問リハビリが予定されていたので、作業療法士さんの見立ても聞き、どうやら足は順調に回復しているようです。であれば、帰京していいはずですが。
それでも遠距離介護を延長した理由
骨折は順調に回復していますが、それでも遠距離介護を延長した理由は日常生活です。医師から、こんな一言がありました。

再転倒だけ注意してくださいね
回復するにつれ、母は立ちあがる回数は増え、歩くスピードも速くなっています。この原稿は実家の2階で書いていますが、途中3回ほど立ち上がって歩き出すのをカメラで確認できたので、ダッシュで1階に行って見守ったほどです。まったく記事に集中できません。
食器を持って移動する、ズボンを両手で上げるなど、壁などで体を支えていない状態になると、ものすごく不安定になります。必ずどこかに手をつかないといけないのですが、認知症です。
骨折したことは忘れ、手を付く大切さを覚えられません。だから何回も何回も何回も手をつく動作を体で覚えてもらうべく指導していますが、たぶん効果はないです。
デイサービスの利用を増やすとわたしはラクですが、おそらく家に居るときよりも歩く時間、立つ回数は少なくなると思っています。自宅のほうがリスクが取りやすいですし、リハビリになる。本当はわたしがいないほうがもっとリハビリ効果はありますが、ひとりは転倒のリスクが最も高いです。
妹と話し合いをして、医師が言った痛みの取れる6月末までは人の見守りを続けていくことになりました。結局、1週間で腹は括れなかったわけですが、ちょっとずつ目を離す練習をしています。骨を折ったあとも、なかなか大変な介護は続きます。
今日もしれっと、しれっと。

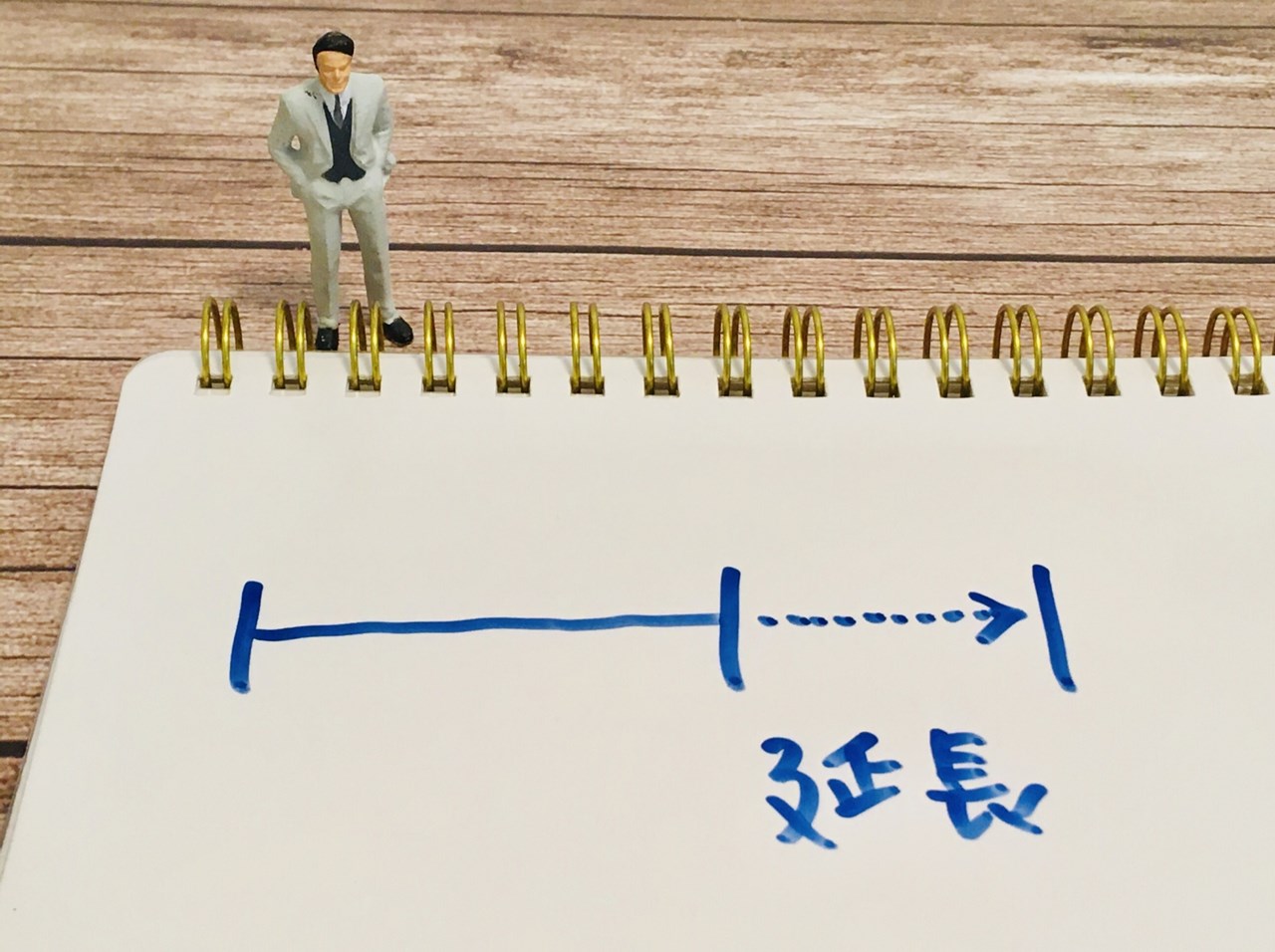














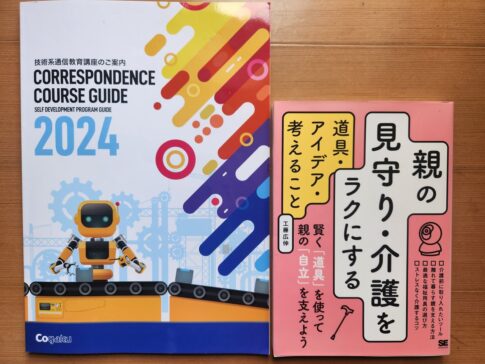



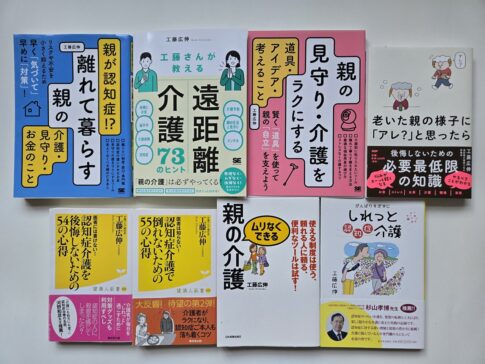











母が足が痛いと言っているのは、骨が治るプロセスの一環でしょうか? それとも再転倒して、他にどこか骨が折れているのでしょうか?