文章で書いた事はありますが、表形式で表示したのは初めての 「我が家のケアプラン」。
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 日曜日 | ||
| 月曜日 | 訪問看護(60分) | |
| 火曜日 | 燃えるゴミ出し(30分) 買い物(45分) | |
| 水曜日 | 訪問リハビリ(40分) | |
| 木曜日 | ||
| 金曜日 | 買い物(45分) | |
| 土曜日 |
見ての通り、ブログのサブタイトルの 「ひとりでがんばらない」 を実践しています(笑)週4日はヘルパーさん、看護師さん、作業療法士さんが来るので、遠距離介護が成り立っています、東京にいても安心です。
今の悩みは 「生きがいと張り合い」
このケアプランに落ち着くまで1年ちょっとかかってますが、これでなんら問題はありません。が、認知症の中でもピック病の母は、アルツハイマー型認知症よりも改善の可能性があります。
薬物療法でウィンタミンを少しだけ試してみましたが、少量過ぎたのか特に変化はありません。今のいちばんの悩みは、母にどうやって「生きがい」や「張り合い」を持たせるかということです。
薬物療法3割、非薬物療法7割
作業療法士さんと現在取り組んでいる 「生活行為向上マネジメント」 は、母に漬物を作らせて知っている人に振る舞うという目標を持たせる事で、生活に「張り合い」を持たせて、社会的役割を果たしてもらうというステキな取り組みです。
ちなみにこのサブタイトルは、BPSD(周辺症状:徘徊や暴力、妄想など)の対応はこの割合という言い方をした先生がいると、上田諭さんの「治さなくてよい認知症」に書いてあったものです。
非薬物療法っていうと何か特別なもの?と考えてしまいますが、要は本人と接する時間を増やして、話をするとかケアを濃密にするということです。本物の薬と偽薬を投与して実験したら、効果は変わらなかったという実験結果もあるようです。
この割合が本当だとすると、非薬物療法はとても重要で、認知症のお薬 < 漬物作り ということになるわけです。そう考えると、ケアプランの作成も非常に重要になるわけで、自分でできる事は自分でやらせたほうがいいのです。認知症のお薬<ケアプラン という優先順位になります。
漬物は実はテストしたのですが、3年ぶりに作ったせいかレシピを思い出せずテストは失敗。本番用に大量にきゅうりを予約したので、本番では成功させたいんですよね・・・
いつもお世話になっている看護師さんや作業療法士さん、ヘルパーさんに漬物を振る舞って、喜んでもらう。その喜びで「張り合い」を感じてもらって、認知症の周辺症状が改善するという青写真をわたしは描いてますが、うまくいくかな~

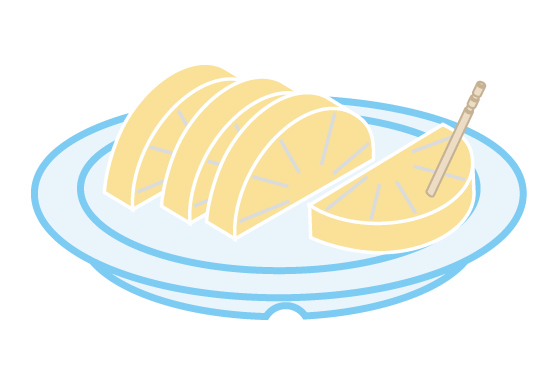




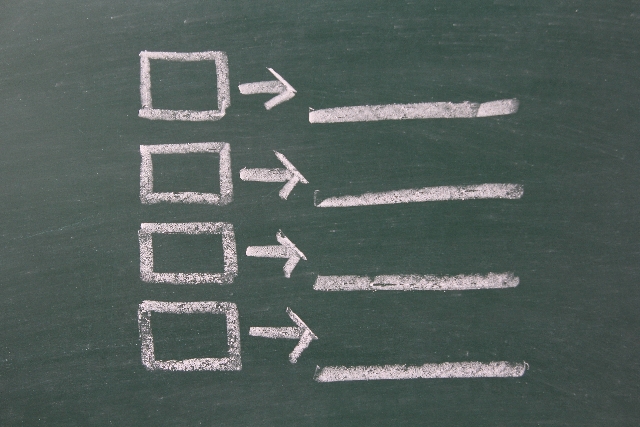





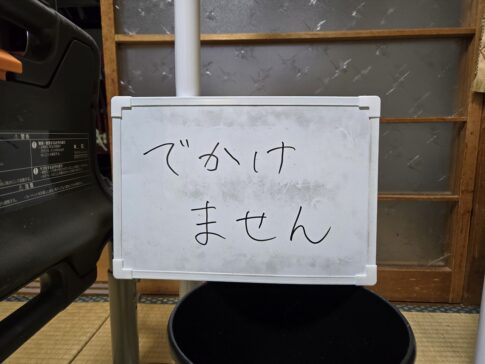



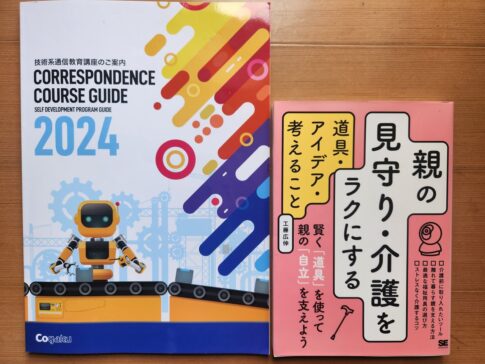



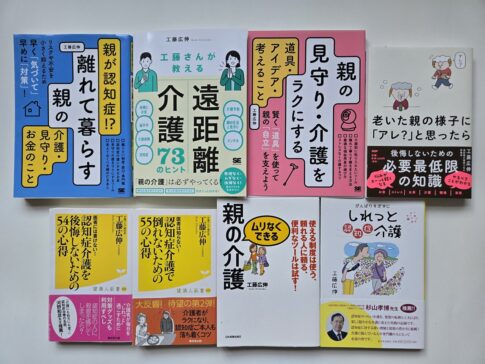








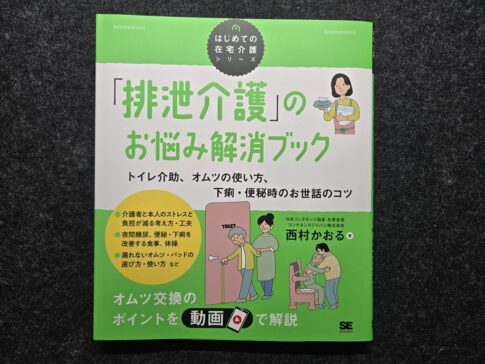


コメントを残す